フリーケンシー(frequency)
「フリーケンシー(frequency)」について、DTM用語の意味などを解説
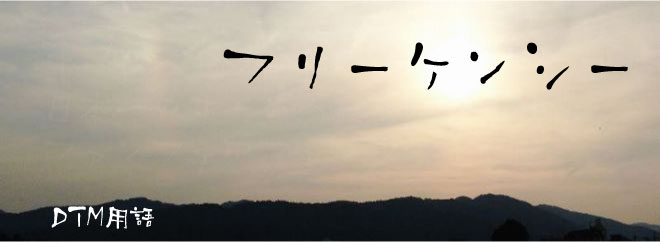
フリーケンシー(frequency)
フリーケンシー(frequency)は、イコライザーやフィルターで使用される音域。ブースト/カットの位置を決定する。フリーケンシー(frequency)とは、「周波数」のことであり、音波が1秒間に何回振動するかを示す物理量で、単位はHz(ヘルツ)で表される。音楽制作においては、これが音高と音色、そしてミックス全体の明瞭さに深く関わる要素として機能する。
人間の可聴範囲

人間の可聴範囲は一般に20Hz〜20kHzとされ、低域(ロー)は20Hz〜250Hz、中域(ミッド)は250Hz〜4kHz、高域(ハイ)は4kHz〜20kHz程度に分類される。たとえば、バスドラムやベースは100Hz以下にエネルギーが集中し、ボーカルの明瞭さは2kHz〜5kHz、ハイハットやシンバルの輝きは10kHz以上に存在する。このようにフリーケンシーの帯域ごとに音の役割が明確に分かれているため、DTMでは帯域のバランスを理解することが極めて重要となる。
EQ(イコライザー)やフィルター処理では、特定の周波数帯域を強調したり削ったりすることで、音の印象や立ち位置をコントロールする。たとえば、150Hz付近をカットすれば「こもり」が軽減され、5kHzを持ち上げれば「抜け」が良くなる。つまり、フリーケンシーのコントロールこそが、ミックスの透明度と音像の定位に直結するのである。また、シンセサイザーにおけるオシレーターのチューニングやフィルターのカットオフ周波数設定も、周波数そのものを操る行為であり、音色の性格や動きに直結するパラメーターである。制作において耳が慣れてくると、100Hzと500Hzの違いを感覚的に聴き分け、意図を持って操作できるようになる。フリーケンシーは、音を「見る」「触れる」ための座標軸といえるだろう。
「フリーケンシー(frequency)とは」DTM用語としての「フリーケンシー(frequency)」の意味などを解説
Published:2025/04/17 updated:
