FM音源
「FM音源」について、DTM用語の意味などを解説

FM音源 Frequency Modulation(周波数変調)
FM音源は、金属的な音色を得意とする電子音源のこと。ドラム、ベース音を出すのが得意で、80年代のポピュラー音楽や、80年代半ば~90年代前半のゲーム音楽に広く使われた。FM音源は、単純な波形の周波数を別の波形で変調することで、複雑で豊かな倍音構造を生成し、デジタルシンセシスの一形態として位置づけられる。この技術の特徴は、従来の加算合成や減算合成では難しかった鋭く硬質な金属的な音色や、複雑でダイナミックな音色変化をリアルタイムで作り出せる点にある。DTMでは、FM音源はベース音、パーカッション、エレクトリックピアノなど幅広い音色に利用され、特に80年代から90年代のポップスや電子音楽において多用された。
DTMにおけるFM音源とは、「Frequency Modulation(周波数変調)」技術を用いた音源であり、1980年代にヤマハのDX7が登場して以来、多くの音楽制作環境で重要な役割を果たしている。FM音源はDTMにおいて独特の表現力を持つシンセシス方式であり、クラシックな電子音から現代的なサウンドメイクまで幅広く活用される重要な音源技術である。
FM音源の構成要素

FM音源の構成要素には「オペレーター」と呼ばれる単純な波形発振器があり、これらが「モジュレーター」と「キャリア」として相互に変調を行うことで、複雑な波形が生成される。多くの場合、複数のオペレーターが組み合わされ、アルゴリズムによってその接続パターンが決まる。DTMソフトやハードウェア音源は、このオペレーターの数やアルゴリズムの種類を選択・編集することで多様な音色を生み出す。
一方で、FM音源は操作が直感的でないことが多く、パラメータ調整には高度な理解が必要とされるため、プリセットを活用するケースが多い。しかし、近年のソフトウェアシンセサイザーではビジュアルインターフェースの改良やモジュールのわかりやすい配置により初心者でも扱いやすくなっている。
FM音源の代表的な音色
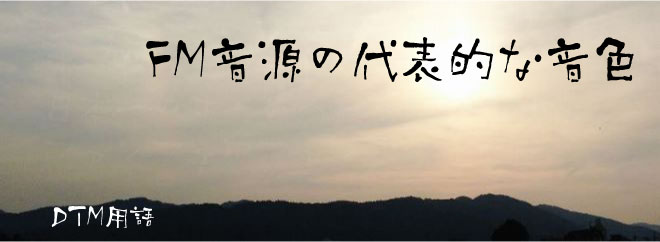
FM音源でよく知られる代表的な音色には、エレクトリックピアノ、ベース、ベル、パーカッション系が挙げられる。これらはFM音源の特徴である倍音の豊富さや鋭いアタック、金属的な質感を活かしたものだ。まずエレクトリックピアノ音色は、DX7の代名詞的存在であり、柔らかくも芯のあるタッチ感と独特の煌びやかな倍音成分が特徴である。FMのオペレーターによる複雑な周波数変調が、まるで金属製の音板を叩いたような繊細な響きを生み出し、ポップスやジャズで広く使われた。代表的な音色は、FM音源が持つ「単純波形の組み合わせから多彩な倍音を生成し、独特のキャラクターを作り出す」という本質をよく表しており、DTMにおける音作りの基盤として今なお多く活用されている。
ベース音色は、低音域でありながらもクリアで抜けの良いサウンドが得られる。FM音源特有の高調波構造により、単なる低音の塊ではなく、明瞭で存在感のある音が作れるため、エレクトロニック系の楽曲で重宝される。
パーカッション音色では、キックやスネア、ハイハットなどの打楽器も、FMの複雑な波形合成を使うことで独特なサウンドを生成できる。特に電子ドラムやトム系で個性的な響きを求める際に効果的である。ベル系音色は、透明感と鋭さを併せ持ち、カリッとしたアタックが特徴的だ。金属的な倍音を多く含み、ハープシコードや鉄琴のような質感を簡単に作り出せるのもFM音源の強みである。
「FM音源とは」DTM用語としての「FM音源」の意味などを解説
Published:2025/04/15 updated:
