ディーティーエム(DTM)
「ディーティーエム(DTM)」について、DTM用語の意味などを解説
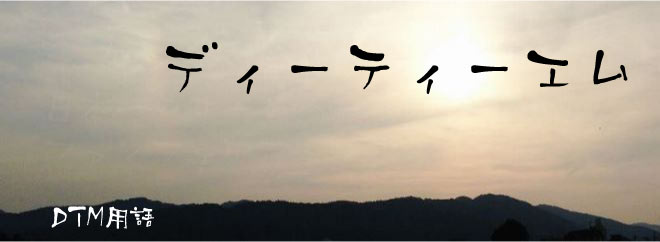
ディーティーエム(DTM)
ディーティーエム(DTM)は、パソコンによる音楽制作。デスクトップミュージック。Desk Top Music。DTM(デスクトップミュージック)とは、DAW(Digital Audio Workstation)を用いてMIDIシーケンスやオーディオトラックを編集・制作する音楽制作手法である。パソコンやソフトウェア、周辺機器を用いて音楽を制作すること全般を指す和製英語で主にDAW(Digital Audio Workstation)で制作。海外では「コンピューターミュージック」や「ホームレコーディング」と表現されることが多い。音源モジュールやVSTiプラグインを駆使し、サンプルベースやシンセシス技術による多層的なサウンドデザインが可能である。DTMは、特別な楽器の演奏スキルがなくても、パソコンとソフトウェアがあれば誰でも手軽に音楽制作を始められる。DAW(Digital Audio Workstation)ソフトウェアは、DTMに使うソフトウェアで、作曲、打ち込み、録音、編集、ミキシングなど、音楽制作のあらゆる作業を一元的に行える。
MIDIノートのベロシティ、CC(コントロール・チェンジ)、オートメーションを用いたダイナミクスとエフェクトの変化管理は、音楽的表現の幅を拡張する。ミキシング段階ではEQによる周波数帯域の分離、コンプレッサーやリミッターでのダイナミクス制御、ステレオイメージャーを用いた定位調整が必須である。マスタリング工程においてはLUFS(Loudness Units relative to Full Scale)を基準とした音圧調整や、True Peak制限によるクリッピング防止が重要視される。現代DTMは、プリセット依存から脱却し、自作プリセットやモジュラーシンセの利用、さらにはサウンドスカルプティング技術の深化が求められている。これにより個性的かつ高解像度な音響空間の構築が実現される。
DAW(Digital Audio Workstation)の選定
現代の音楽制作において、DAW(Digital Audio Workstation)の選定はもはや制作フロー全体を規定するファクターとなりつつある。たとえば、Ableton Liveのシーンクリップベースのアプローチは、ミニマリズムやループ主体のエレクトロニック・ミュージックに最適化されているのに対し、CubaseやLogic Proでは従来型のリニアなMIDIアレンジメントやスコアエディットを多用する作曲家にとって強い親和性を持つ。これらの違いは単なるUIレベルの話ではなく、オートメーションの扱い、内部バウンス処理、さらにはリアルタイムレンダリング時のCPUリソースの配分まで含めて、音楽のアウトプットに影響を与える構造的差異である。
「構造的なアプローチ」と「音響的視点」
DTM制作経験を重ねるにつれプリセット音源とテンプレート構成に頼りすぎた結果として現れる「制作の停滞感」、そしてミックス段階で感じる「音の迷子」に迷いが出ることがある。コードは鳴っている、ドラムも走っている、しかしトラック全体の像が立ち上がらない。何を直せばよいのか分からず、EQとコンプで延々と微調整を繰り返すというのがDTMの中〜上級者が陥りやすいループだ。そうした状況を打破するための「構造的なアプローチ」と「音響的視点」から、DTMにおけるトラックメイキングを再構築する手法を提案する。目的は“音楽を作ること”ではなく、聴かれる音像を建築すること”である。音楽的設計図としてのMIDI、階層的音色設計、定位と空間の制御、さらにはリズム構造の物理的制御、そしてマスタリングにおける空間最適化までを技術的・音響的に解剖していく。
音楽的スケッチからの構造設計
多くのDTM制作者がトラック制作に入る際、まずMIDIノートでコードを置き、ドラムを配置し、ベースを合わせていく。しかしこの「積み木方式」は、サウンドが積層的になっていく一方で、音楽の全体像、とりわけ音像の立ち上がりに関しては極めて曖昧なまま進行してしまうことがある。ここでは、構造を意識した「音響的スケッチ」の手法を紹介する。
MIDIノートでコードを書くのではなく空間を書く
通常、和声進行としてMIDIでコードを記述するが、ここではむしろ「音の質量」として捉える視点が重要になる。たとえばAm7というコードであっても、その鳴らし方次第で“質量感”は大きく変わる。CとEをオクターブで強調しつつ、Gをサブ的に配置することで「中央定位の密度」を強調することができる。つまり、MIDIノートは音階の羅列ではなく、空間における音の配置図として扱うのが鍵だ。
セクションごとのダイナミクス構成とコンプレッショングリッド
イントロ、Aメロ、Bメロ、サビといった構成を設計する際、多くはコードとビートをベースに考えがちだ。しかし、プロフェッショナルなトラックにおいては、セクションごとの音圧バランスやスペクトル分布の密度こそが“聴感上の流れ”を作っている。たとえばサビに向かって音圧(≠音量)を段階的に持ち上げるために、各セクションにおいてマルチバンドコンプレッサーの帯域ごとの動きを綿密に設計する。こうしたコンプレッショングリッドの発想があれば、フェーダーを上げなくても盛り上がりは設計できる。
メロディではなくレイヤーとしてのライン設計
従来のメロディ設計では「主旋律」を中心に考えるが、現代のトラックメイキングではレイヤー構造としてのライン設計が主流だ。たとえばLo-fi HipHopにおけるリードシンセは、単なるメロディではなく「中高域を支える質感の1パート」として設計される。その結果、単体で聴くと地味なフレーズであっても、全体のトラック内では“情報量”の一部を担い、音像形成に寄与する。ここで重要なのは「良いメロディ」ではなく「音像の中での居場所」である。
プラグインエコシステムとサチュレーション
プラグインエコシステムもまた、DTM環境における音像形成の肝を握る。たとえば、コンプレッサーひとつ取っても、FET系(1176タイプ)とOpto系(LA-2Aタイプ)ではアタック/リリースの挙動が根本的に異なり、トランジェント・シェイピングに対する感度にも明確な差がある。リダクションの効き方が倍音構造にどう作用するかを意識しなければ、ローエンドが無駄に膨らんだり、スネアのアタックが埋もれてしまったりするのは当然の帰結である。また、サチュレーションの活用に関しても、単に「温かみを足す」といった漠然とした理解では不十分だ。テープ系サチュレーター(たとえばSoftube TapeやUAD Ampex ATR-102)とトランス系(Waves Kramer Master TapeやSlate VTM)では、倍音の生成特性が異なり、特定帯域のフォーカスを強調するか、全体的なコヒーレンス(密度感)を付与するかといった点で運用が分かれる。
MIDIプログラミングとミックス
MIDIプログラミングにおいても、ベロシティ・レイヤーの設計次第でモックアップのリアリズムは大きく変化する。単純なラウンドロビンだけでは不自然な反復感を拭えず、そこでノート・オフのタイミングやエクスプレッション・カーブを含めた詳細なコントロールチェンジ(CC)のオートメーションが求められる。とくにストリングス系ライブラリでは、キー・スイッチの管理とアーティキュレーションマッピングの最適化がリアルタイム再生における自然なフレーズ構築の鍵となる。
ミックス段階においては、位相整合とステレオイメージングがトラックの分離感を決定づける。マルチマイクで収録されたドラムやアンビエンスの音源に対して、MS処理(Mid/Side Processing)を用いることで、サイド成分にリバーブを寄与させつつセンターのパンチを維持する、といった高度なバランス調整も一般的となってきた。また、マスター段階ではLUFS値の管理とTrue Peakの制御が、ストリーミング・プラットフォーム向けのラウドネスノーマライゼーションにおいて重要視されている。
「ディーティーエム(DTM)とは」DTM用語としての「ディーティーエム(DTM)」の意味などを解説
Published:2025/04/16 updated:
