アフター・タッチ(after touch)
「アフター・タッチ(after touch)」について、DTM用語の意味などを解説
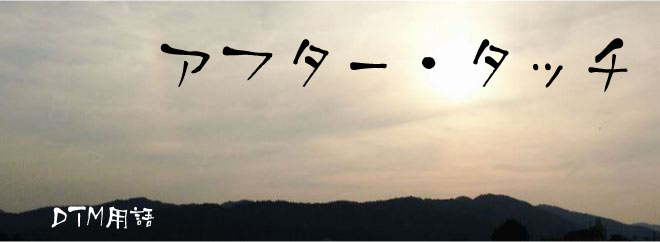
アフター・タッチ(after touch)
アフター・タッチ(after touch)は、鍵盤を押した状態で、さらに鍵盤を押し込むことによって音量増加やモジュレーションの効果を付加する機能を指す。ビブラートや音色の明るさなどを調整する機能。アフター・タッチとは、鍵盤楽器やMIDIキーボードにおいて、鍵盤を押した後の追加的な圧力に応じて音色や音量、エフェクトを変化させる表現機能である。一般的に、鍵盤を押し込んだ直後にさらに加える圧力が検知され、その信号がMIDIメッセージとして送出されることで、演奏中にリアルタイムで音色の変化やビブラート、フィルターの変調などが可能となる。この機能は、表現力の向上や演奏のダイナミクスを拡張する手段として、現代の電子楽器やシンセサイザーにおいて広く利用されている。
豊かな演奏表現のために有効な機能のひとつである。
なお、アフター・タッチにはMIDIチャンネル別に効果が得られるチャンネル・プレッシャー(ポリフォニックキープレッシャー)、各鍵ごとに個別の効果が得られるキー・プレッシャーの2種類がある。
1970年代には、ヤマハのCS-80を初めハイエンドのシンセサイザーに搭載され始め、その後はMIDIの1機能としても定義された。音色への影響はデータを受信するMIDI音源に依存するが、アフタータッチに音量の変化やピッチの変化を割り当てておき、ブレスコントロールのようなビブラートをかけたりする、などといった使用方法がある。
DTM環境では、アフター・タッチは音色設計やシンセシスにおける重要なパラメーターとして組み込まれる。シンセサイザーのエンベロープやLFO、フィルターカットオフ、モジュレーションデプスなどの各種パラメーターにアフター・タッチを割り当てることで、演奏中にリアルタイムで音色の変化やダイナミクスを操作できる。この特性は、特にリード音やパッド、シンセベースの演奏において、表現力を飛躍的に向上させる。
また、アフター・タッチはライブ演奏や即興演奏においても重要である。演奏者は鍵盤上で微細な圧力を加減するだけで、従来のピアノやギターのような表現の揺らぎや強弱を再現でき、電子楽器特有の平坦な音に自然な生気を与えることができる。このため、アフター・タッチ対応の鍵盤はプロフェッショナルな音楽制作やパフォーマンスにおいて重宝される。
「チャンネル・アフタータッチ」と「ポリフォニック・アフタータッチ」
アフター・タッチには主に「チャンネル・アフタータッチ」と「ポリフォニック・アフタータッチ」の二種類が存在する。チャンネル・アフタータッチは、鍵盤全体の圧力を平均化してMIDIチャンネル単位で信号を送る方式であり、全音域に一括でエフェクトをかけたい場合に有効である。
一方、ポリフォニック・アフタータッチは、各鍵盤ごとに独立して圧力を検知し、個別の音に対して変化を加える方式である。これにより、和音演奏中でも各音ごとにビブラートやフィルターの変化を与えることが可能となり、より表現豊かな演奏が実現する。
「アフター・タッチ(after touch)とは」DTM用語としての「アフター・タッチ(after touch)」の意味などを解説
Published:2025/04/15 updated:
