S/N比
「S/N比」について、DTM用語の意味などを解説

S/N比(Signal to Noise Ratio)は、シグナル/ノイズ(S/N)の割合を示したもの。
- シグナル=音の本来の成分
- ノイズ=雑音や耳では聞き取れないような低周波や高周波の雑音等
この比率が高いほど幅広い帯域での音の再現性に優れ、不快な雑音の割合が少ない。
db(デシベル)で表記する。信号に対するノイズの量の対数。S/N比(Signal to Noise Ratio)は、有用な信号(Signal)に対するノイズ(Noise)の比率をdB(デシベル)単位で表す音響工学上の基本指標である。SNR(Signal to Noise ratio)。信号レベルとノイズフロアとの差を意味し、その値が大きいほど「音の明瞭度が高い=ノイズの影響が少ない」と解釈される。たとえば、S/N比が90dBであれば、信号がノイズよりも90dB分だけ大きいことを意味する。音響機器やオーディオインターフェース、マイクプリアンプ、デジタルコンバータ(ADC/DAC)などにはこのS/N比のスペックが明記されており、高S/N比の機材は低ノイズでクリアな収録・再生が可能である。プロフェッショナル用途では、S/N比100dB以上がひとつの目安とされる。
S/N比は単なる数値ではなく、音質管理と表現力の土台を支える設計哲学であり、制作・録音・ミックス各工程における重要な判断基準となるべきである。DTMにおいても、音源やトラック単位でのS/N意識は重要である。ノイズが目立つボーカルトラックや、サンプル元に含まれる環境ノイズ、さらにはプラグインによるアナログ・モデリングノイズ(ヒス・ハムなど)も、最終的なミックス/マスタリング時に影響を及ぼす。ローカットやノイズゲート、リストレーションツール(例:iZotope RX)などを用いて適切に管理することが推奨される。
S/N比の物理的・設計的な対策
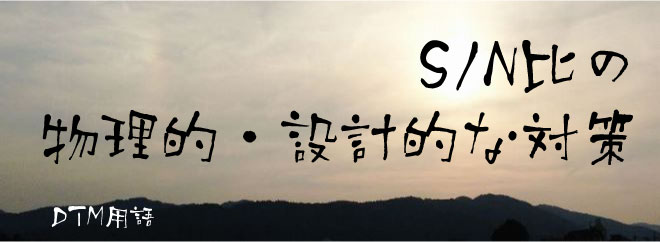
S/N比は、単にスペック表の数値を見るだけでは不十分であり、実際の運用においては、ゲイン・ストラクチャーの最適化や、アナログ配線の整理、グラウンドループの排除、バランス接続の活用など、物理的・設計的な対策が不可欠である。たとえば、入力ゲインが低すぎれば信号レベル自体がノイズに埋もれ、結果的にS/N比が低下する。逆に過剰なゲインブーストはクリッピングや歪みを引き起こすため、適切なレベルマネジメントが要求される。
量子化ノイズ(quantization noise)
.jpg)
また、デジタル領域では、量子化ノイズ(quantization noise)もS/N比に影響を与える要因であり、24bit以上のビット深度で録音・編集を行うことで、理論的には144dB超のS/N比が確保可能である。これにより、ノイズの影響を最小化しつつ、広いダイナミックレンジを維持することが可能となる。
S/N比の向上
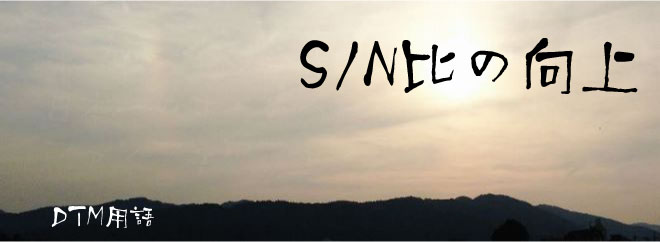
S/N比を向上させるためには、まず信号レベルを適切に確保しつつ、ノイズ要因を最小限に抑えるという二軸のアプローチが求められる。第一に重要なのは、正しいゲイン・ストラクチャーの構築である。入力段階で十分なゲインを確保することで、信号がノイズフロアに埋もれるのを防ぐ。ただし過度なブーストは歪みの原因となるため、入力レベルは適正値(例:-12dBFS前後)を維持すべきである。また、バランス接続(XLR/TRS)を用いることで、外部ノイズ(電磁干渉・グラウンドループ等)に対する耐性が大きく向上する。とくに長距離のオーディオケーブルを使用する環境では、アンバランス接続(TS/RCA)はノイズの温床となる。
さらに、電源環境の整備も重要である。オーディオインターフェースやモニターにはクリーンな電源供給を行い、PCや照明などノイズ源とは別回路に接続することが望ましい。フェライトコアやアイソレーターの導入も有効である。そして、DAW内部では不要なノイズ要素を除去するために、ノイズゲート、ハイパスフィルター、エディットによる無音処理を活用すべきである。録音素材に含まれるヒスノイズや環境音は、必要に応じてリストレーションツール(例:iZotope RX)で処理する。
S/N比は音の「質」を支える基礎であり、制作現場全体で意識的に管理・最適化されるべきパラメータである。
1st Published:2013/05/10
「S/N比とは」DTM用語としての「S/N比」の意味などを解説
Published:2025/06/09 updated:
