打ち込み
「打ち込み」について、DTM用語の意味などを解説
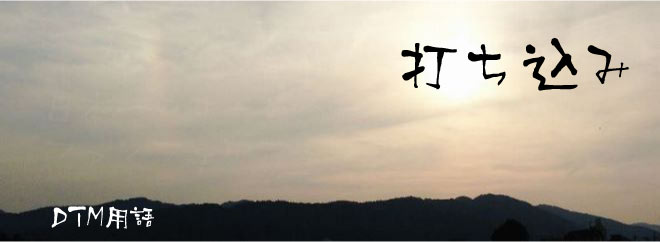
打ち込みは、シーケンサーやシーケンサー・ソフトに演奏データを入力すること。打ち込みもの。シーケンサーやコンピューターに入力した演奏データによってシンセサイザーなどの電子楽器を自動演奏させ、人間の生演奏には望めない正確無比なリズムやフレーズを得る、という手法を取り入れた音楽作品/アレンジを指す通称。俗にいう「同期もの」もほぼ同義で使われる。
打ち込みとは、DTM(デスクトップミュージック)や電子音楽制作において、実際に演奏するのではなく、シーケンサーやDAW(Digital Audio Workstation)、リズムマシンなどの機材・ソフトウェアを用いて音符やリズムパターンを入力し、楽曲を構築していく手法を指す。
英語では「programming」や「sequencing」とも呼ばれ、MIDIデータを基盤に音源モジュールやソフトシンセを鳴らす形で発展してきた。日本語特有の表現として「打ち込み」という言葉が定着しており、エレクトロニック・ミュージックのみならず、ポップス、ロック、映画音楽、ゲーム音楽などあらゆる分野で用いられている。
打ち込みはDTMの根幹を成す概念であり、作曲や編曲、サウンドデザインにおいて不可欠なプロセスである。正確性と自由度を兼ね備えたこの手法は、単なる補助技術を超えて、現代音楽のスタンダードな制作方法として確立している。
打ち込みの起源は、1970年代後半から1980年代にかけて普及したシーケンサーやドラムマシンに遡る。Roland TR-808やLinnDrumなどの機材を用いてリズムをプログラムする行為が「ビートを打ち込む」と呼ばれたことから、日本語としての「打ち込み」が一般化した。
その後、MIDI規格の登場により、ピアノロール画面でノートを入力したり、外部キーボードを使ってリアルタイム録音したデータを編集したりするワークフローが確立した。現在ではDAW上でのピアノロール編集が中心となり、音長、ベロシティ、タイミングを細かくコントロールすることが可能である。
打ち込みの大きな特徴は、人間が演奏する際に生じる揺らぎや制約を超え、完全に正確なリズムや極端なテンポ、複雑なポリリズムなどを自在に構築できる点である。これにより、テクノやトランスといったエレクトロニック・ダンス・ミュージックはもちろん、映画音楽における大規模オーケストレーションのモックアップ制作や、アニメ・ゲームの劇伴におけるシンセサウンドの構築など、多様なジャンルで活用される。
一方で、打ち込みが「機械的すぎる」と感じられる場合もあるため、意図的にベロシティやクオンタイズをずらして「人間味」を加えるテクニックが存在する。これを「ヒューマナイズ」と呼び、MIDI編集の重要な要素となっている。また、近年のソフトウェア音源は生演奏のサンプリングやアーティキュレーションを豊富に備えており、打ち込みによっても極めてリアルな表現が可能になっている。
打ち込みは「演奏の代替」ではなく、新しい音楽表現を生み出す手段としても機能している。例えば、ドラムマシン特有のリズムパターンやシーケンサーによるステップ入力は、実演奏では不可能なリズム構造を創出し、ジャンルそのものの個性を形成してきた。エレクトロ、ヒップホップ、ハウスといったジャンルは、打ち込みがなければ成立し得なかった音楽である。
「打ち込みとは」DTM用語としての「打ち込み」の意味などを解説
Published:2025/04/15 updated:
